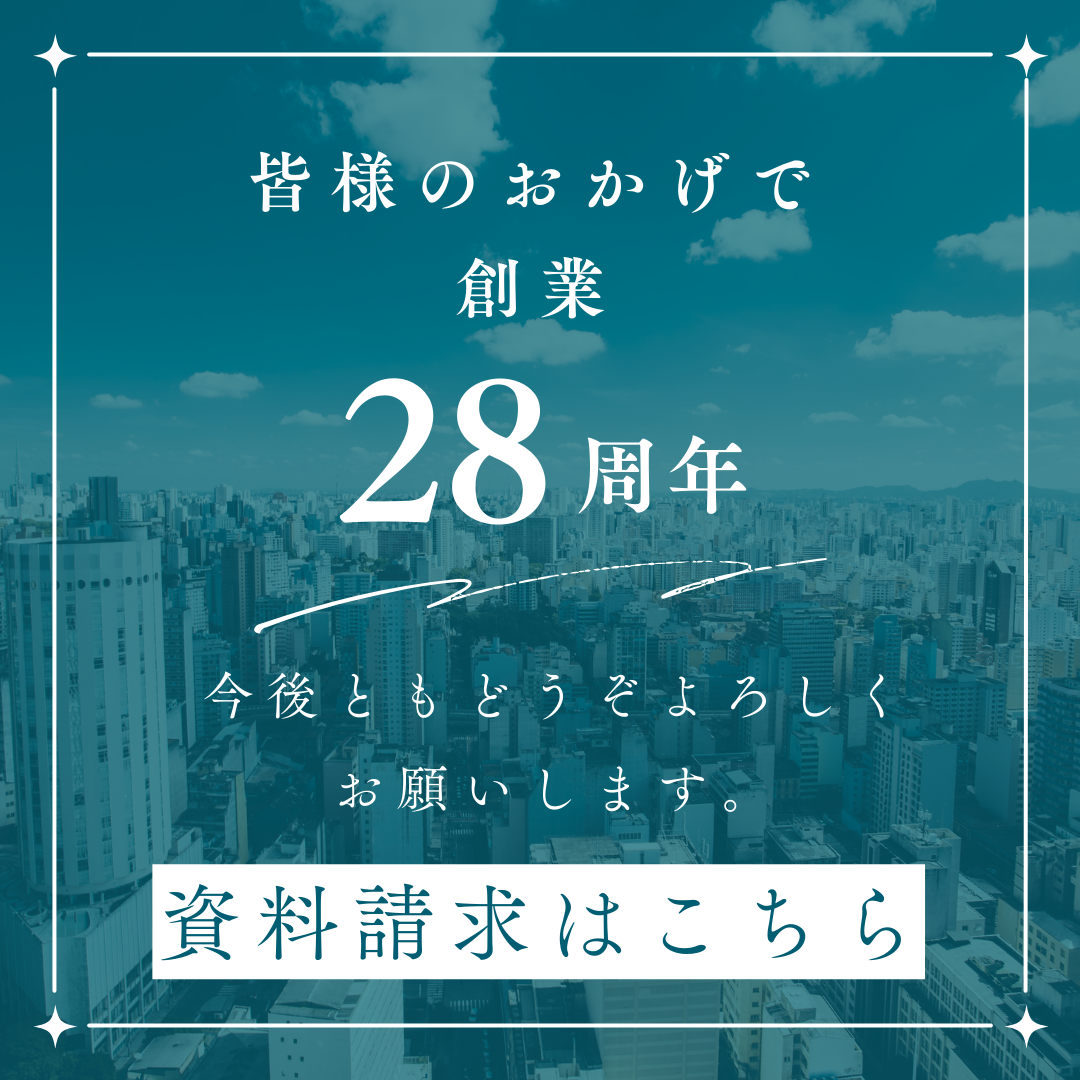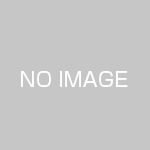国際輸送の重要な部分を担うフォワーダー。
フォワーダーと聞いて、どんな仕事をしているかすぐに思い浮かべることが難しい職業かもしれません。
もしくは、貿易をやっていても、実際のところどんな役割を果たしていて、貿易の流れの中でどの部分を任せられるのか、はっきりしない職業かもしれません。
そこで今回はフォワーダーについてわかりやすい解説をしていきたいと思います。
フォワーダーとは
フォワーダーは日本名で言うと「貨物利用運送事業者」の事を指し、簡潔に言えば、フォワーダー(英語表記:forwader / a freight forwarder)は、不特定の荷主から貨物を預かり、自社の船舶や航空機を利用するのではなく、他の事業者の運送手段(航空会社・船会社)を有効利用する貨物利用運送事業者のことを差し、海外の荷主と日本の荷主の輸送を仲介する役割を果たすのがフォワーダーの業務となります。
つまり、日本製品を輸出して販売したい企業、海外現地の販売会社、あるいは海外商品を日本に輸入したい企業と、国内に販路を持つ日本企業の仲介をしているのが「フォワーダー」となります。
現在、世界では、インターネット等の普及により、海外からの物の動きがより活発になった事で、以前よりもさらに国際物流ビジネスは消費者にとっても身近なものになってきております。
しかし、実際に企業等が直接国際物流のビジネスを行うとなると、煩雑な手続きや国ごとに異なる規制や関税、法規制など全てを自社で対応していくのには大きな障害が発生してきます、その際にそれらを代行、現地の販売会社との仲介をしてくれるのが、国際物流のプロフェッショナルである「フォワーダー」となります。
なお、あらゆる手段を使い国際輸送を行うのがフォワーダーですが、会社によって航空輸送が得意なフォワーダー、海上輸送が得意なフォワーダー、また両方のサービスが得意なフォワーダーと分けることが出来ます。
海上輸送に強いフォワーダーは主に「NVOCC = Non Vessel Operating Common Carrier」と呼ばれることが多く日本語表記で〝非船舶運航海上運送人〟と呼ばれております。
また航空貨物に強いフォワーダーを「Air Freight Forwarder(エア・フレイト・フォワーダー)」と呼びまれています。弊社OTS Japanをどちらかに分類するとなると、「Air Freight Forwarder」に属する事となります。
前述の通り「NVOCC」も「Air Freight Forwarder」も自ら自社で船舶や航空機を持たずに貨物輸送業務を請け負う事業者となります。双方とも不特定多数の荷主から集めた貨物を集約し、それぞれ船会社or航空会社と委託し貨物の輸送を行います。
つまり、上記と若干だぶりますが不特定の荷主から貨物を預かり、自社の船舶や航空機ではなく、他の事業者の運送手段を活用する貨物利用運送業者を全判的に「フォワーダー」と呼ばれています。
フォワーダーの強み
フォワーダーの最大の強みは、国際物流の専門知識とネットワークを活かし、最適な輸送手段を選択できることです。
特に以下の点で、大きなメリットがあります。
- コスト削減と効率的な輸送ルートの確保
フォワーダーは、多くの荷主の貨物を集約することで、一括契約を結び、航空会社や船会社との交渉力を強化できます。
これにより、個別に手配するよりもコストを抑えつつ、効率的な輸送ルートを確保できます。 - 国際貿易に関する手続きを一括代行
通関手続き、輸出入に関わる書類作成、保険手配などを一手に引き受けることで、荷主の負担を大幅に軽減します。
特に関税や法規制が国ごとに異なるため、フォワーダーの専門知識は不可欠です。 - 輸送中のトラブル対応
天候やストライキ、港湾の混雑など、国際輸送には予期せぬトラブルがつきものです。
フォワーダーは柔軟なルート変更や、代替輸送手段の手配を迅速に行い、スムーズな輸送を維持します。 - 倉庫管理や物流サポート
単なる輸送だけでなく、海外・国内での倉庫保管、ピッキング、梱包などの物流サービスも提供することもできます。
これにより、荷主は在庫管理や納品スケジュールを最適化でき、ビジネスの効率向上につながります。
弊社では、イタリアの展示会での会場の設営や通訳の紹介などのサポートもしております。
このように、フォワーダーは単なる輸送の仲介者ではなく、物流の最適化を支援する重要な役割を果たしています。
特に貿易に関わる企業にとって、フォワーダーの活用は、物流コストの削減やリスク回避の面でも非常に有益なのです。
乙仲、通関業者、フォワーダーの違い
国際物流にはさまざまな専門業者が関わっており、「乙仲」「通関業者」「フォワーダー」は特によく混同される用語です。
ここでは、それぞれの役割や違いについて詳しく解説していきます。
乙仲
結論から言うと、現在では「乙仲」と「フォワーダー」は同じ意味を表します。
戦前からある海運組合法の名残でフォワーダーと同様の意味を表す「乙仲」という名称がいまだに残っていて「乙仲」という言葉が今も使われています。当時は定期船貨物の取次をする仲介業者を「乙種海運仲立業」と呼んでおり、その略語が「乙仲」なのですが、1947年に海運組合法は廃止。現在ではその言葉だけが今も名残として残っている状態です。
また各港湾地区で貨物を取り扱う専門業者を別名「海運貨物取扱業者」と呼びますが、海運貨物取扱業者はフォワーダーと同様に、貨物利用運送業務を行います。ただ海運貨物取扱業者の名称のとおり、港湾地区でのみ貨物を取り扱う専門業者としての部分が強く、荷主の代わりに貨物の船積みの手続き・引取りの手続き・搬出入・運送・荷役など、さまざまな業務を担っています。そんな「海運貨物取扱業者」の旧式の呼び方が「乙仲」という事になります。
ただし、フォワーダーは国際輸送全般を取り扱う業者であるのに対し、海運貨物取扱業者は港湾地区での輸出入業務を中心に活動するという違いがあります。そのため、すべての海貨業者がフォワーダーのように国際輸送業務を行っているわけではありません。
通関業者
通関業者とは、税関から許可を受け、輸出入に関する通関手続きを代行する業者です。
当然ですが、輸出入を行う企業が自ら税関に対して輸出入の申告をすることも可能ですが、特に関税の計算や、国によって異なる貿易規制の対応を誤ると、貨物がスムーズに通関できず、輸送の遅延や追加費用の発生につながることもあります。
そのため、多くの企業は専門知識を持つ通関業者に手続きを依頼しています。
通関業者の主な業務
- 輸出入書類の作成と提出(インボイス、パッキングリスト、B/Lなど)
- 関税や消費税の計算・申告
- 税関への輸出入許可申請
- 検査対応(税関による貨物検査の立ち会い・対応)
フォーワーダー
これまで解説したように、フォワーダー(貨物利用運送事業者)は、海上・航空・陸上輸送の各事業者と荷主の間に立ち、最適な輸送手段を手配する国際物流のプロフェッショナルです。フォワーダーの主な役割は、以下のように幅広い業務をカバーしています。
- 輸送手段の手配(海上・航空・陸上の組み合わせ)
- 通関手続きのサポート
- 貨物の保管・梱包・配送手配
- 国際輸送に関する各種書類の作成
- 輸送中のトラブル対応
また、フォワーダーと呼ばれている業者が通関業務を行ったり、海運貨物取扱業者がフォワーダーと通関を兼ねているケースもあります。
まとめ
フォワーダーは、単に貨物を運ぶだけの存在ではなく、企業の貿易事業全体を支援する役割を果たしています。
また他にも、輸送の最適化、コスト削減、通関手続きのサポート、トラブル対応、物流コンサルティングなど、多岐にわたるサービスを提供し、国際物流の円滑化に貢献しています。特に輸出入を行う企業にとって、フォワーダーの活用は、国際競争力を高めるための重要な戦略のひとつと言えるでしょう。
さらに、三国間貿易といった、複雑な貿易取引にも対応が可能であり、重量物から軽量物はもちろん、陸上・海上・空輸といった、あらゆる輸送手段を使い輸送手配が可能ですので、輸出入を行う企業はそれぞれ自社商品の輸送を得意とするフォワーダーを見つけ輸送業務を委託していくと良いでしょう。
この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら!