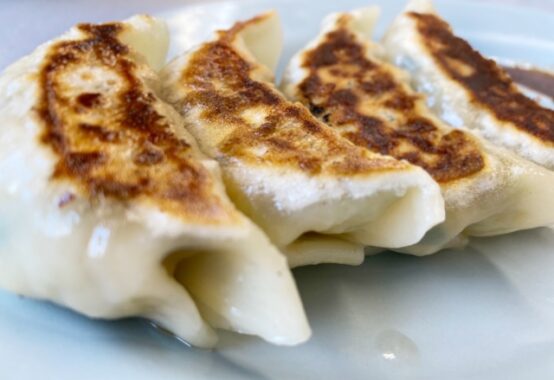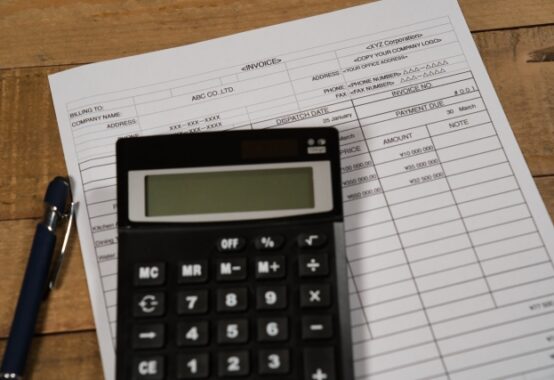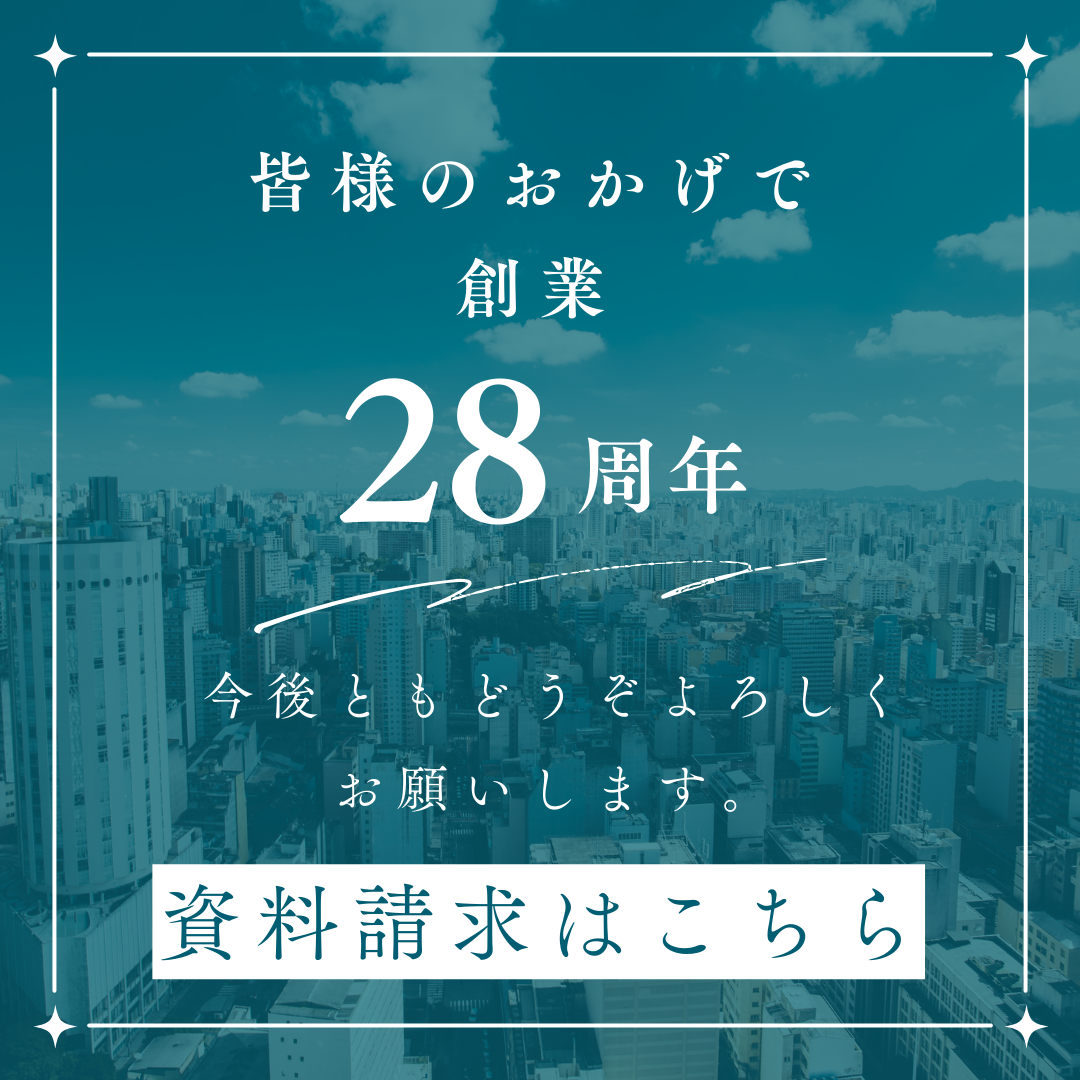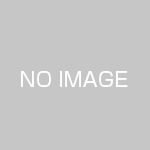コンテナ船輸送で大きな働きをする「ドック・レシート」。
ドック・レシートはコンテナ船輸送の取引の流れの中で、あらゆる方面で活躍する書類です。
貨物がコンテナ輸送の契約をされてから港を離れるまでの流れに沿って、ドック・レシートがどこでどのような働きをしているのか、特徴や注意点を中心にご紹介します。
目次
ドック・レシートとは?基本概要をわかりやすく解説
ドック・レシートは、コンテナ船特有の書類です。
(現在は電子化されていますが、以前は紙媒体でしたので次のような流れて作成されていました。)
ドック・レシートとは、港にあるコンテナを保管するエリア(コンテナヤード/CY)に貨物を搬入した後、コンテナ船の輸送で海貨業者が船荷証券(B/L)を取得するために船会社へ提出する重要な書類です。
ドックレシートのドックは「Dock=波止場」の意味をもち、 D/Rとも略されます。
ドック・レシートの特徴を3つのポイントで解説
コンテナ船で使われるドック・レシートならではの特徴を主に3つお伝えします。
船荷証券(B/L)の引換券としての役割
ドック・レシートは、船荷証券(B/L)の引換券のような役割があります。
「船会社が海貨業者からドック・レシートを受け取った=CY(コンテナヤード)での貨物の引き渡しを確認した」という意味になり、船会社にとってドック・レシートは貨物の受取証明書になります。
海貨業者が船荷証券(B/L)をもらうためには、船会社へのドック・レシートの提出が必須です。
提出したドック・レシートの内容に基づいて、船荷証券(B/L)が発行されます。
1セット8枚構成の理由
ドック・レシートは1セット4~8枚綴りになっていて、業者がドック・レシートを受け取ると1枚ずつ手元に残していきます。
1回のやりとりで終わる書類ではなく、海貨業者や船会社、CY、税関、発送元といったあらゆる業者の手に渡る書類のため、1セット4~8枚で構成されています。(現在は電子化されており、船社専用フォームで申請します。)
FCLとLCLで異なる提出先
同じコンテナ船でも貨物輸送の流れが異なるFCLとLCLでは、ドック・レシートの提出先が異なります。
FCLの場合
FCLの場合には、ドック・レシートとコンテナ明細書をCY(コンテナヤード)オペレーターに提出します。
FCL(Full Container Load)は輸送船をまるごと1つ借りるので、自社の貨物以外は搭載されません。
そのため貨物は直接CYに運ばれるので、ドック・レシートをCYオペレーターに引き渡します。
LCLの場合
LCLの場合は、ドックレシートをCFS(コンテナ・フレート・ステーション)オペレーターに提出します。
LCL(Less than Container Load)は、FCLと違いコンテナ船をまるごと1つ借りない輸送方法です。
そのため一旦貨物は、CFSという貨物を混載する場所(倉庫)に集められ、コンテナに詰めてからまとめてCYに運ばれます。
他社の貨物と合わせて輸送されるLCLの場合には、直接貨物がCYに運ばれるわけではないため、中継地点のCFSオペレーターにドック・レシートを引き渡します。
ドック・レシートの流れと活用方法
コンテナ船が輸送されるために必要なドック・レシートの全体の動きをご紹介します。
- 発送元からシッピングインストラクション(船積依頼書)を受け取った海貨業者は、船会社にドック・レシートを発行する
- 税関から海貨業者に輸出許可書がきたあと、船会社はドック・レシートを海貨業者に戻す
- 海貨業者は、船会社から受け取ったドック・レシートと貨物を一緒ににCY(またはCFS)に搬送する
- 貨物の船積み後、税関にドック・レシートを提出(税関は船積みが完了したことを認識する)
- 残っているドック・レシートは海貨業者に戻す
- 海貨業者が船会社に、残っているドック・レシートのうち1枚を渡すと、船会社から船荷証券(B/L)が発行される
- 船荷証券(B/L)を受け取った海貨業者は、船荷証券(B/L)とドック・レシートを発送元に渡す
以上が、コンテナ船において使われているドック・レシートの流れです。
ドック・レシートはあらゆる場面で必要とされているため、すべてのシーンで1枚ずつ減っていきます。
ドック・レシートの記載内容とその重要性
ドックレシートは船荷証券(B/L) のもとになる書類なので、記載内容やフォームが船荷証券に類似しています。
ドック・レシートの記載内容は、以下のようなものが挙げられます。
- 発送人名(会社名など)
- 予約番号(ブッキング番号)
- 荷受人名(会社名など)
- 荷受人住所
- 船積み港
- 荷揚げ港
- 貨物の個数、重量、大きさ
- 商品内容
- B/L発行地
受け取った貨物に損傷や個数の過不足など異常があった場合は、必ずドック・レシートにその内容が記載されます。
ドック・レシートを扱う際の注意点
ドック・レシートは貨物の受け渡しを証明する重要な書類ですが、取り扱いにはいくつかの注意点があります。
紛失や記載ミスがあると、船荷証券(B/L)の発行に影響が出るため、事前にリスクを把握して適切に管理しましょう。
紛失時のリスクと対応策
ドック・レシートは船荷証券(B/L)の基礎データであり、紛失するとB/Lの発行ができなくなる可能性があります。
そのため、以下のような、紛失時のリスク管理と迅速な対応策を講じることが重要です。
紛失時の主なリスク
- B/Lの発行が遅れる → 輸送スケジュールに影響が出る。
- 貨物の受け取りができなくなる → 輸入者側にトラブルが発生する可能性。
- 船会社やフォワーダーとの調整が必要 → 追加の手続きが発生する。
対応策
- 電子化されたデータを活用する(近年、多くの船会社が電子ドック・レシートを導入)。
- ドック・レシートのコピーを事前に確保する。
- 船会社やフォワーダーに速やかに連絡し、再発行の可否を確認する。
- 代替書類(搬入証明書など)で対応できるか確認する。
また、一部の船会社ではドック・レシートの発行を必要としないケースもあるため、利用する船会社のルールを事前に確認しておくことが大切です。
船会社ごとのフォーム規定の把握
ドック・レシートのフォーマットや記入方法は船会社ごとに異なるため、書類作成時には十分な注意が必要です。
ポイント
- 船会社の指定フォーマットを使用する。
- 記入方法のルール(手書き・電子データなど)を確認する。
- フォームの最新バージョンを使用しているかチェックする。
また、ドック・レシートはシッピングインストラクション(船積依頼書)や船荷証券(B/L)と密接に関連しています。
これらの書類の規約やフォームが変更された場合、ドック・レシートの仕様も変更される可能性があります。
よって、スムーズな取引を実現するためにも常に最新の情報を確認し、必要に応じてフォワーダーや船会社へ問い合わせを行いましょう。
在来船との違いに注意
ドック・レシートが使用されるのは、コンテナ船で輸送するFCL(Full Container Load)およびLCL(Less than Container Load)のみです。
在来船との違い
- コンテナ船(FCL・LCL) → ドック・レシートが必要。
- 在来船(Break Bulk Cargoなど) → ドック・レシートを使用しない。
在来船は、コンテナ輸送が適さない大型貨物や特殊貨物の輸送に使用されるため、ドック・レシートではなく別の貨物受領証が用いられることが一般的です。
輸送方式によって必要書類が異なるため、貿易業務に携わる際には注意しましょう。
ドック・レシートとシッピングインストラクションとの違いを解説
「ドック・レシート(D/R)」と「シッピングインストラクション(S/I)」の記載内容は似ていますが、活躍するタイミングが異なります。
「シッピングインストラクション」は、発送元が海貨業者に発行する書類です。
貨物の情報や通関依頼など、発送元が海貨業者に指示を出す書類になります。
「ドック・レシート」は、海貨業者から船会社に発行される書類です。
海貨業者が発送元から受け取ったシッピングインストラクションに基づき、ドック・レシートは船会社に発行されます。
ドック・レシートとシッピングインストラクションの違いを知るには、コンテナ船の船積書類の流れを把握することが大切です。
どちらも似た情報を記載しますが、目的が異なるため混同しないようにしましょう。
まとめ:コンテナ船で大活躍のドック・レシート
コンテナ船特有の種類である、ドック・レシートについてご紹介しました。
ドック・レシートの特徴をおさらいすると、以下の通りです。
- 船荷証券(B/L)の引換券
- 1セット8枚の書類
- FCLとLCLで発行先が異なる
ドック・レシートは、発行元からのシッピングインストラクションを元に作成され、船荷証券(B/L)のもとになる、取引の橋渡しの役割があります。
書類の全体の流れから、しっかりドック・レシートの特徴や注意点を把握しておくことで、スムーズな取引に貢献できます。
この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら!