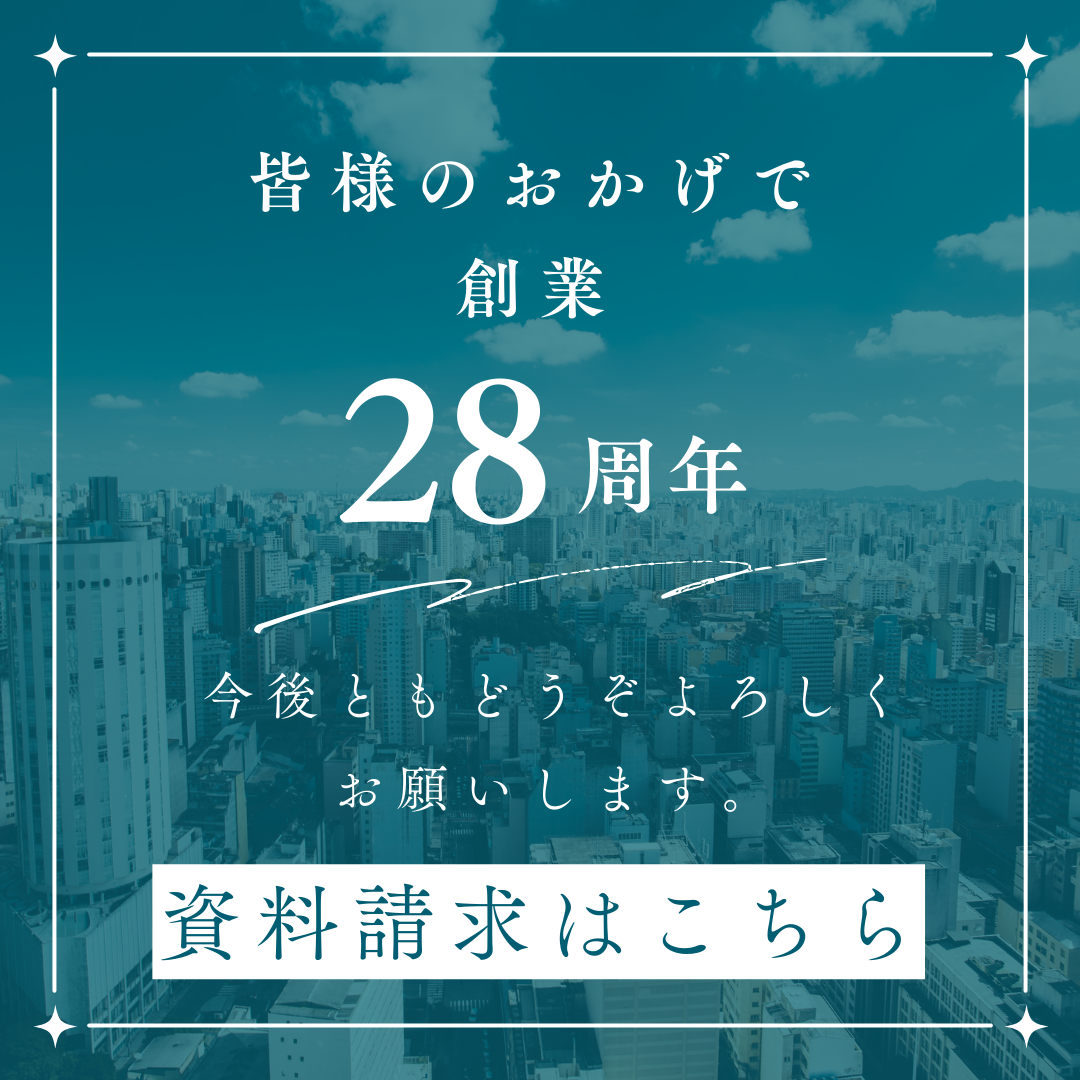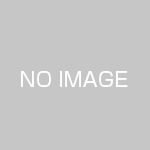今回は、D/O(デリバリーオーダー)についてご紹介します。
D/Oは港で輸入貨物を引取る際に必要となる書類です。
ほとんどの輸入の場合、輸入者は通関業者等の物流業者に輸入に係る一連の業務を委託していることが一般的であり、基本的にはその業者がD/Oの入手を含めて対応してくれます。
そのため、輸入業務を担当している方であっても、D/Oを見たり聞いたりした事がない方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、D/Oは港で貨物を引取る際に必要となる大切な書類であり、特に自ら港へ貨物を引取りに行く方であれば、必ず知っておかなければなりません。
D/Oとはどのような書類であるのか、確認してみましょう。
当記事では、次のような内容に沿ってお伝えします。
目次
D/Oの役割と重要性
D/Oとは荷渡指図書のことで、Delivery Orderの略です。
D/O(デリバリーオーダー)は、輸入貨物を引き取る際の「鍵」となる重要な書類です。
この書類が適切に発行・管理されることで、港湾や倉庫でスムーズな貨物引き渡しが実現します。
また、D/Oは貨物の引き渡し権限を証明する役割も持ち、取引における安全性を確保するための重要な手段です。
一方、D/Oの不備や発行遅延は、輸送スケジュールやコストに大きな影響を及ぼすため、確実な手続きが求められます。
D/Oの入手方法
D/Oは、船会社やフォワーダーにB/Lを提出することで入手できます。
B/L(Bill of Lading、船荷証券)は、貨物の所有権を証明する重要な書類です。
輸出者から輸入者に貨物とは別に送られ、通常、船が港に到着する前に輸入者の元へ届きます。
コンテナ船の場合、D/Oの取得手順は以下の通りです:
- B/Lの準備
輸入者は、輸出者から受け取ったB/Lを確認し、不備がないかをチェックします。
特に、船会社名や貨物の詳細が一致していることを確認してください。 - 船会社での提出
港に貨物が到着した後、船会社またはフォワーダーにB/Lを提出します。
これが、D/Oを発行してもらうための必須条件です。 - D/Oの受領
B/Lと引き換えに、D/Oが発行されます。
ポイントとして、B/Lが手元にない場合や内容に不備がある場合、D/Oの発行が遅れることがあります。
これにより、貨物引き取りに影響が出るため、事前準備を徹底することが大切です。
また、オンライン手続きを導入している船会社も増えており、事前登録を行えば手続きがスムーズになります。
貨物の引取る際に必要な書類
港に到着した貨物を引き取るには、主に以下の書類が必要です。
これらの書類が揃っていなければ、貨物の引き取りはできません。
- D/O(デリバリーオーダー)
D/Oは、船会社とB/Lを交換することで入手します。
前述の通り、D/Oは貨物引き渡しの指示書であり、港湾管理者や倉庫が貨物を引き渡すために必要な書類です。 - 輸入許可書
輸入許可書は、貨物を輸入する際に必要な税関の正式な許可書です。
税関に輸入申告を行い、書類審査や貨物検査が完了した後に発行されます。
基本的にこの許可書を入手しない限り、貨物を引き取ることはできません。
書類が揃っていない場合の注意点
D/Oや輸入許可書の不備や遅れがあると、貨物の引き取りができず、以下のリスクが生じる可能性があります:
- 保管料の増加:倉庫での保管期間が長引き、追加料金が発生する。
- 輸送遅延:その後の配送スケジュールが大幅にずれる可能性がある。
効率的な書類準備のためのポイント
- 事前確認を徹底する
D/Oや輸入許可書の取得状況を事前に確認し、不足がないよう準備を整えましょう。 - タイムラインを把握する
船の到着日や通関手続きにかかる時間を把握し、配送スケジュールに余裕を持って対応することが重要です。
港での貨物引き取りの流れ:貨物到着からD/O取得まで
港に貨物が到着してから、貨物を引き取るまでの基本的な流れをご紹介します。
各ステップを確実に進めることで、スムーズな引き取りが可能です。
船会社から到着通知
港に貨物が到着した後、あるいは到着する2日程度前に、船会社から輸入者に対して到着が通知されます。
このときの通知は、アライバルノーティス(Arrival Notice)と呼ばれる書類で、一般的にA/Nと略されます。
A/NはメールやFAXで届き、輸入申告の際に必要です。
さらに、A/Nには以下の情報が含まれることがあります:
- 海上運賃
- THC(ターミナルハンドリングチャージ)
- CFS費用(コンテナフレイトステーション費用)
これらの費用をB/LとD/Oを交換する際に支払うこととなります。
通関手続き
貨物がCY(コンテナヤード)またはCFS(コンテナフレイトステーション)に搬入された後、税関に対して輸入申告を行います。
輸入申告時には、以下の書類を税関に提出します:
- インボイス
- パッキングリスト
- B/L
- A/N(アライバルノーティス)
注意点として、税関には書類のコピーを提出し、原本を渡さないようにしましょう。
輸入申告が受理されると税関で審査が行われ、問題がなければ輸入許可が発行されます。
B/LとD/Oの交換
通関手続きが完了した後、船会社にオリジナルのB/Lを提出します。
同時に、A/Nに記載されている費用(海上運賃やTHCなど)を支払います。
船会社がこれらの書類と支払いを確認した後、D/O(デリバリーオーダー)を発行してくれます。
このD/Oは、次の貨物引き取りで必要となる重要な書類です。
貨物引取り
D/Oと輸入許可書を携えて、CYまたはCFSに貨物を引き取りに行きます。
どちらか一つでも欠けていると、貨物を引き取ることができませんのでご注意ください。
貨物の引取り時に搬出予約や搬出料が必要なこともあるため、
必要な手順や追加費用については、事前に確認しておくとスムーズです。
完了
輸入の一連の流れは以上で完了となります。
補足:手続き順序について
なお、「4.2.輸入通関手続き」と「4.3.B/LとD/Oの交換」は前後入れ替わっても大丈夫です。
ただし、貨物の引取り時にはD/Oと輸入許可書が必要ですので、「4.4.貨物引取り」の前には両方を済ませなければなりません。
D/OレスとサレンダーB/Lの注意点
ここまでD/Oについて解説してきましたが、あくまで基本的な流れになります。
貨物の引き取り方法には、状況や船会社のサービスによってD/OレスやサレンダーB/Lといった代替手段があります。
それぞれの特徴と注意点を以下で詳しくご説明します。
D/Oレスの場合
オリジナルBLの場合、CY(コンテナヤード)またはCFS(コンテナフレイトステーション)で貨物を引き取る際には、書類としてのD/Oが必要です。
しかし、D/Oレスではその名のとおり、D/Oの書類提出が不要となります。
- 手続き簡素化のメリット
書類のやり取りが不要になるため、貨物引き取り手続きが迅速化されます。
特に、書類が紛失するリスクや、輸送中の遅延リスクを軽減できます。 - 事前の申し込みが必要
D/Oレスを利用するには、事前に船会社へ申し込み、D/Oレスの処理を依頼する必要があります。
注意点
また、オンラインシステムや事前登録が必要な場合があるため、利用条件を確認しておきましょう。
コロナ禍をきっかけにD/Oレス化が進んでおり、今ではほとんどの船会社がD/O LESSに対応しております。
サレンダーB/Lの場合
サレンダーB/Lは、貨物が輸出地から輸入地に到着する際、オリジナルB/L(船荷証券)を必要としない仕組みです。
オリジナルB/Lは輸出地の船会社で回収され、「Surrendered」というスタンプが押されます。
サレンダーB/Lのメリット
- 書類到着の遅延リスクを回避
通常、輸入者が貨物を引き取るにはオリジナルB/Lが必要ですが、輸送中の遅延で到着が間に合わないことがあります。
サレンダーB/Lでは、オリジナルB/Lが不要となるため、貨物引き取りの迅速化が可能です。 - 簡略化された手続き
船会社に提出するのは輸出者からFAXやメールで送られてきたサレンダーB/Lのデータのみです。
オリジナルB/Lの到着を待つ手間が省略されるため、時間とコストを削減できます。
注意点
- すべての輸入に対応しているわけではない
サレンダーB/Lは輸出者と輸入者の双方が合意の上で使用される仕組みです。
合意がない場合や、船会社が対応していない場合には利用できません。 - セキュリティリスク
データのやり取りが主流となるため、情報漏洩や不正使用のリスクが高まる可能性があります。
取引相手や船会社の信頼性を確認しておくことが重要です。
基本的な流れとの違い
サレンダーB/LやD/Oレスは、従来のオリジナルB/Lを必要とする方法と比べて簡素化された仕組みです。
また、全ての輸入手続きに対応しているわけではないため、利用する際は以下を事前に確認しましょう。
- 船会社の対応状況
- 必要な事前手続きや登録内容
- 商品代金回収等のリスク
こうしたポイントを押さえることで、より効率的な貨物引き取りが可能となります。
まとめ
今回は、D/Oについて、基本的な輸入海上貨物の引取り方をご紹介しました。
D/Oは輸入許可書と併せて港に到着した貨物を引取る際に必要となる大切な書類です。
通関業者などの物流業者に輸入に係る一連の業務を委託している場合、D/Oを直接目にすることはないかもしれません。
ただ、D/Oレス処理を船会社に申込めば貨物をより早く引取りやすくなるなど、輸入者にとってメリットがある事もあります。
また、港へ自ら貨物を引取りに行く方であれば、D/Oについて必ず知っておかなければなりません。
D/Oについてさらに確認したい事がある場合には、起用物流会社等に相談してみても良いでしょう。