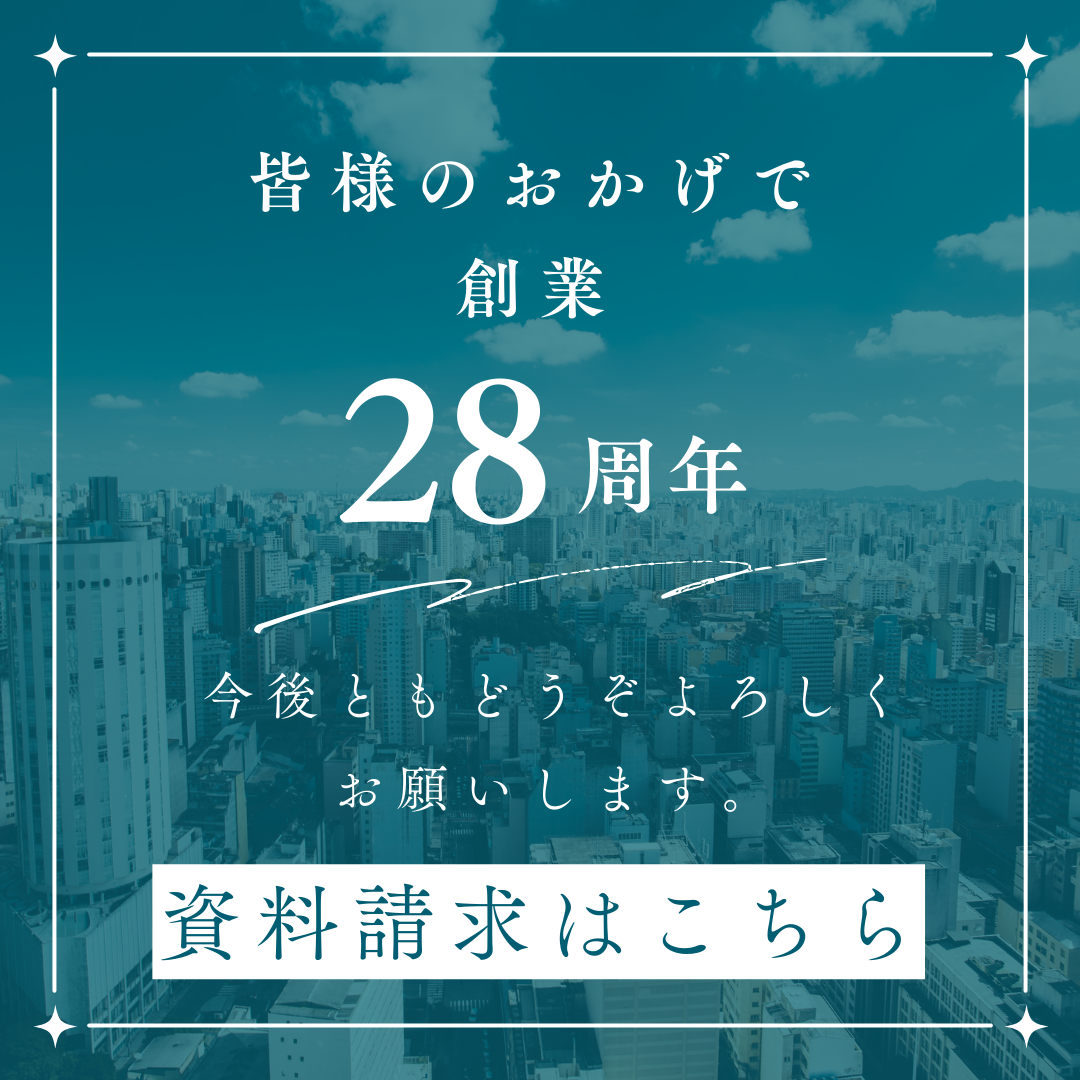フリータイム、デマレージ、ディテンション。
海外から輸入を定期的に行なっている荷主様であれば、多くの方が聞いたことのある言葉だと思います。
コンテナが輸入された時、荷主様はもちろんのこと、船会社も早くコンテナを引き取ってもらいたいですよね。
そこで、港にコンテナを置いておける期間や、コンテナを返却する最長貸出期間を制限し、それ以上の延滞期間の追加料金を「フリータイム」「デマレージ」「ディテンション」と呼びます。
今回は、そのルールに関してチェックしてみたいと思います。
目次
フリータイムとは?猶予期間とルール
コンテナ単位での輸入の場合、本船から荷下ろしされたコンテナを荷主様が引き取るまでの猶予期間。船社によって設定は異なりますが、ドライコンテナの場合で搬入確認日より6~7営業日ほど無料保管となります。
デマレージとは?発生条件と料金の仕組み
フリータイムを超過した場合、日数に応じて課される保管料金は『デマレージ』と呼ばれます。これは船社がコンテナを効率よく回転させるため(荷下ろし完了後の空バンを次の輸出用コンテナとして使用するため)の手段です。
ドライコンテナの場合は下記のような設定がされています。
20’ Dry 40’ Dry
1~4日: JPY5,200 per day / JPY7,750 per day
5~9日: JPY12,400 per day / JPY18,600 per day
10日~: JPY20,700 per day / JPY31,000 per day
上記のように非常に高額になるため、絶対に避けるよう管理が必要です。
筆者自身、業界に入りたての頃に輸入コンテナをCYに放置して5万円くらいのデマレージ請求を受けたことが何度かあり、上司にボロクソ怒られたのを今でもハッキリと覚えています(笑)。
デマレージを回避するための管理ポイント
デマレージは、適切なスケジュール管理を行うことで回避可能です。下記のポイントに注意しましょう。
フリータイム内に貨物を引き取るための事前準備
・通関書類(インボイス・B/L・パッキングリスト)を早めに準備する
・貨物到着前に通関業者と打ち合わせし、確認が必要な部分を調べる
・事前に税関検査の可能性がある貨物について確認しておく
トラックや倉庫の手配を事前に確定
・港でのコンテナ滞留を防ぐため、貨物到着前にトラックの確保を完了
・引き取りが混雑する時期(繁忙期、年末年始)は特に早めの手配が必要
船会社との事前交渉でフリータイム延長を検討
・大口荷主や定期輸送契約がある場合は、フリータイム延長の交渉が可能
・フォワーダー経由で船会社と調整することで、デマレージのリスクを低減
ディテンションとは?延滞料金の詳細
荷主様がCYから実入りコンテナを引き取った後に空バンをCYに返却するまでの間の延滞料金です。
荷主様によっては貨物の特性上、実入りコンテナ受け取り後、バン出し作業を完了するまで4~7日かかったりする場合もあるようです。
ディテンションが発生する背景と目的
コンテナは船会社の資産であり、世界中を循環して貨物輸送に使用されるものです。
そのため、長期間荷主側で保管されると、次の輸送に回せなくなるため、船会社は回転率を維持する目的でディテンションを設定しています。
特に、輸出入の貨物量が増加している昨今では、コンテナの供給不足が発生しやすいため、船会社は迅速な返却を求める傾向が強まっています。
コンテナ搬出日より起算して4営業日は無料、以降は下記のような費用が発生します。(船社にとって変わります。)
20’ Dry 40’ Dry
1~4日: JPY2,100 per day / JPY4,100 per day
5~9日: JPY3,100 per day / JPY6,200 per day
10日~: JPY5,200 per day / JPY10,300 per day
ディテンション発生の主な原因
- 貨物の特性によるバン出し作業の遅延
・精密機器や高額商品など慎重な作業が求められる貨物
・多品種・小ロット貨物の仕分けに時間がかかる場合 - 倉庫の受け入れ遅延
・倉庫スペースの確保が間に合わない
・フォークリフトや作業員不足による荷降ろし遅延 - トラック手配の遅れ
・コンテナ返却のためのドレーが確保できない
・繁忙期による物流の混雑
フリータイム延長の方法と注意点
デマレージ発生を事前に回避するため、積み地(海外)にて事前にフリータイム延長契約を船社と締結する場合もあります。
BL上に “14 days Free at Destination” などと記載されている場合はその証明となります。ただし現状では世界的にコンテナ不足が慢性化しており、当然ながら船社としてはフリータイム延長を受けない傾向が強くなってきています。
ディテンションはフリータイム(通常4営業日)が経過した時点から発生し、日数が長くなるほど単価が上昇する仕組みになっています。
長期間の返却遅延はコストの増大につながるため、適切なスケジュール管理が求められます。
ディテンションを回避するための管理ポイント
- 事前に荷降ろしスケジュールを確定する
・バン出し作業の必要時間を把握し、コンテナ返却の目処を立てる
・可能であれば、フリータイム内に作業を完了させる - 倉庫・物流会社との連携を強化する
・倉庫スペースの事前確保を行い、受け入れの遅れを防ぐ
・作業員の確保やフォークリフトの手配を早めに済ませる - トラック手配を確実に行う
・返却予定日をドライバーと調整し、直前のトラブルを回避
・繁忙期は特に早めに予約を入れ、返却可能な日程を確保 - 船会社とフリータイム延長の交渉を行う
・長期的な取引がある場合、事前交渉によってディテンションの猶予期間を延長できる可能性がある
・フォワーダーを通じた交渉も有効です!
フリータイム短縮のリスクと影響
ここ最近の世界的なコンテナ不足により、船社はより効率的にコンテナを流通・回転させるためルールを変更する場合も出てきているようです。
中国系船社においては中国発~日本向け輸入Reeferコンテナについて2021年10月よりFree Time無しを適用しているようです。こうなると輸入元してはどれだけ急いでもデマレージが発生するため結果的にコスト増につながってしまいます。予想は困難ですが、この流れは他船社にも広がっていく可能性もあります。
(参考)中国発Reeferコンテナ デマレージ
20’ Reefer 40’ Reefer
1~4日: JPY5,000 per day / JPY5,000 per day = フリータイム無し
5~7日: JPY9,000 per day / JPY13,500 per day
8-12日: JPY18,000 per day / JPY27,000 per day
13日以降: JPY36,000 per day / JPY54,000 per day
以上はコンテナ単位の輸入の場合の話ですが、次に混載貨物LCLの場合のフリータイムです。
CFSフリータイムの仕組み
コンテナを陸揚げ ~ CFSにコンテナ横持ち ~ コンテナ出し作業 ~ マーク確認 ~ 搬入確認が上がるまでに現状、入港日より1~3日かかっています。
CFSの場合は搬入確認日より起算して通常は5~7日間のフリータイムが適用されます。こちらも混載業者によって設定は異なります。
到着~荷受手続きの流れを解説
コンテナ、LCLの両方の場合の搬出手続~貨物受取に関してもどのようにして書類やコンテナや貨物が流れていくのか解説していきたいと思います。
輸入者様の大事な商品を搭載したコンテナですが、当然ながらその扱いは厳重なルールの下で行なわれており、所定の手続きを踏まないとコンテナを引取りに行ってもピックアップできません。
輸入コンテナ引き取りのプロセス
コンテナ船の入港から陸揚げまで
輸入コンテナの引き取りは、以下のステップで進行します。
- コンテナ船の入港・コンテナの陸揚げ
ガントリークレーン(赤と白のキリンのような形をした巨大クレーン)を使い、コンテナ船から埠頭へコンテナを陸揚げ
陸揚げされたコンテナは**船社のCY(コンテナヤード)**へ搬入
コンテナ番号を確認し、システムに搬入完了情報を登録 - 船会社の費用支払いとB/L(船荷証券)の確認
船会社の海上運賃・港湾費用の入金を確認
貨物引き取りに必要なB/L(船荷証券)またはWaybillの処理を完了
NACCS(税関システム)上で貨物の引き取り許可が出たことを示す「Y表示」を確認
通関手続きと税関審査
貨物の引き取りには、事前に税関での通関手続きを完了させる必要があります。
- 通関業者が税関へ輸入申告
必要書類(インボイス・パッキングリスト・B/Lなど)を税関に提出
審査がスムーズに進めば、輸入許可が即日取得可能 - 税関による審査(必要に応じて検査実施)
定期的に輸入している品目の場合は、問題なく輸入許可が出るケースが多い
初回輸入の貨物や特定の税番(関税分類)の場合は、税関の審査対象となることがある書類審査 → X線検査 → 開披検査とより詳しい検査が行われます。
大型エックス線検査の重要性
エックス線検査は、税関による水際対策の一環として実施されており、不正輸入の摘発にも活用されています。
例えば、密輸事例として覚せい剤などの違法薬物が商品の中に隠されていたケースがあり、エックス線検査によって発見されたこともあります。
コンテナの引き取りと配送
- ドレー業者(トラック会社)がコンテナをピックアップ
輸入者は、ドレー業者(運送会社)にコンテナの引き取りを依頼
運送会社はDispatch(コンテナ搬出票)をCYに提出し、コンテナをピックアップ - コンテナの輸送と荷降ろし(デバンニング)
実入りコンテナを輸入者の指定倉庫へ運搬
倉庫でコンテナから貨物を取り出し(デバンニング作業)
荷降ろし完了後、コンテナは空バン状態となる - 空バンの返却(ディテンション回避)
荷降ろしが終わった空バンは、指定のCYへ返却
フリータイム内に返却しないとディテンション(コンテナ延滞料)が発生するため、迅速な対応が必要
大まかに上記のような作業を経て商品の受け取りが完了します。
以前は書類のやり取りがもっと複雑で、船社に支払い完了後にD/O (Delivery Order)原本を発行してもらい、それをドライバーに渡してコンテナピックアップに向かっていましたが現在ではD/O Lessが当たり前になって大幅に効率化されています。
まず重要になるのが船社への支払い完了とWaybill確認です。支払が完了していてもBLが元地回収もしくはWaybillに切り替わっていない場合はコンテナ引き取りができません。
税関による審査
定期的に同じ品目を輸入している場合は審査なしで輸入許可になる場合が多いですが、例えば初回輸入の荷主様の場合や、または審査に引っ掛かりやすい品目(税番)の場合など、税関検査になる場合がございます。
大型エックス線検査
コンテナごとエックス線装置を通過し、内部の積み荷を税関職員がチェックする。これは税関による重要な水際対策なのですが、事例として、コンテナ内の商品の中に覚せい剤を隠して密輸する事例をエックス線検査で摘発する場合もあります。
これら作業を全てフォワーダー、通関業者に委託する輸入者様が多いのが現実ですが、たまに税関に出向いたり、あるいはターミナルの入庫待ちのコンテナの列を見ると本当に手間のかかる大変な作業だなと感じる事ができるかと思います。
LCL輸入 貨物引き取りまでの流れ
LCLの場合も基本はコンテナと同様の流れですが、複数荷主様の貨物が同一コンテナに搭載されているため、コンテナ陸揚げ後に一旦CFS (Container Freight Station、保税倉庫)へ横持ちし、コンテナ出し~搬入確認作業の流れになります。
ここ2~3年はハブ港の保税倉庫 & ドレー逼迫により、現在では入港から2~3日後にようやく搬入確認~輸入申告に入るという流れが主流です。
そこでよく問題になるのがマーク確認です。複数荷主様の貨物を仕訳ける際に、保税倉庫の作業員は当然ながら梱包を開ける事は絶対にありません。
基本は梱包外装にあるマークでどの荷主様の貨物か確認~データを反映させるのですが、輸入においてはマーク無しの貨物が含まれている場合が多々あり、これを輸入元に確認する作業が発生する場合があり作業時間が長引く原因となりますが、貨物を間違って配送(テレコ)すると大変な問題となるため保税倉庫としては厳重に管理しています。
輸入許可後はそれぞれ物量にあわせたトラックでCFSに貨物ピックアップに向かいますが、こちらもコンテナと同様に混雑によりCFSで受付後、数時間の搬出待ちになる場合が多いようです。
大井ふ頭の最近の状況(2021年10月時点)
2か月ほど前に久しぶりに大井ふ頭に行ったのですが、相変わらずのコンテナドレーの搬入待ち・搬出待ちの大行列、CFS搬出待ちのトラックの列、路上駐車で順番待ち、の車両だらけでした。CYが早朝オープンして効率を上げる取り組みもされてはいるようですが、現実的には更に物流が逼迫しているイメージを受けてました。
関係者による少しずつの改善の積み重ねが問題解決につながり、物流に関わる人々全員の環境が改善される事を心より祈っています。
この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら!