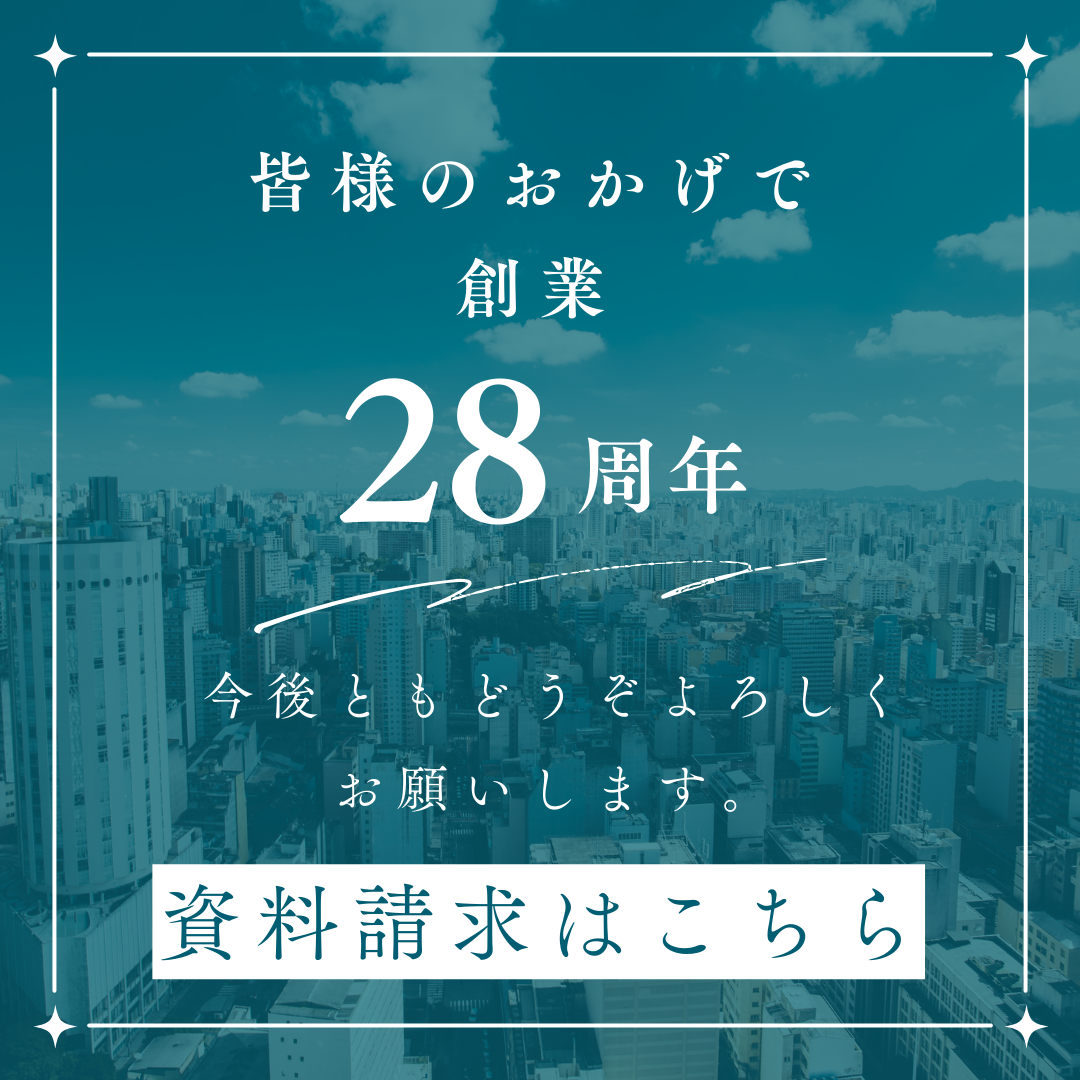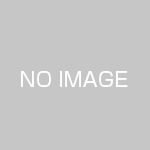貿易取引には、2国間貿易以外にも、3国間貿易があります。
3国間貿易は、「仲介貿易」とも呼ばれています。
当記事では、3国間貿易の概要、モノ・カネ・カミの流れ、必要な書類手続き、メリット、デメリットについて詳しく解説をしていきます。
当記事を読むことで、一見難しそうに見える3国間貿易について理解することができるでしょう。
目次
3国間貿易とは?基本概要と特徴を解説
3国間貿易とは、輸出者と輸入者の間に仲介業者が加わる特殊な貿易形態で、モノ(貨物)、カネ(支払い)、カミ(書類)がそれぞれ異なるルートで流れる点が特徴です。
例えば、以下のような形で取引が行われます。
- 輸出者 :マレーシア
- 仲介業者:日本
- 輸入者 :オーストラリア
この場合、実際の貨物はマレーシアからオーストラリアへ直送されますが、日本の仲介業者が売買契約や決済をコントロールします。
中継貿易・間接貿易との違い
3国間貿易と似た貿易形態として、「中継貿易」と「間接貿易」があります。
それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
| 貿易形態 | 貨物の流れ | 決済の流れ | 仲介業者の関与 | 代表的な例 |
| 3国間貿易 | 貨物は輸出国から輸入国へ直送 | 仲介業者を経由して決済 | 仲介業者が取引を管理(書類・決済調整) | 日本の商社がシンガポールから米国に商品を販売 |
| 中継貿易 | 一度第三国を経由し、そこから輸入国へ再輸出 | 中継国を通じて決済される場合もある | 中継国で関税や再輸出の手続きが発生 | 香港を経由して中国へ輸出するケース |
| 間接貿易 | 仲介業者が一度商品を買い取り、輸入者へ販売 | 仲介業者が商品を所有し、独自に売買 | 仲介業者が販売価格を自由に設定 | 日本の商社が国内企業から商品を購入し、欧州へ販売 |
このように、3国間貿易は貨物が輸出国から直接輸入国へ届けられる点が大きな特徴です。
一方、中継貿易では第三国を経由し、間接貿易では仲介業者が実際に商品を所有するため、手続きやコストの違いが生じます。
それでは、次に3国間貿易の「モノ・カネ・カミ」の流れについて詳しく解説していきます。
3国間貿易のモノ・カネ・カミの流れを解説
3国間貿易には、以下の特徴があります。
- 製品は輸出国から輸入国へ直接輸送される
- 書類とお金の支払いは第3国にいる仲介業者を経由する
モノの流れ
3国間貿易といっても、製品が輸出者→仲介業者→輸入者という流れで輸送されるわけではありません。
物の流れについては、2国間貿易と同様に、輸出者から輸入者へ直接製品が送られます。
オカネの流れ
3国間貿易では、輸入者と輸出者で直接決済をするのではなく、仲介国を通して支払いが行われます。
3国間貿易のお金の流れは下記の通りです。
- 輸出者が仲介業者に対して請求を行う
- 仲介業者は、輸出者からの請求額にマージン分を加算した金額を、輸入者に対して請求する
- 輸入者から仲介業者に支払いが行われる
仲介業者がマージンによる利益を得ることが、3国間貿易の特徴の1つです。
カミの流れ
通常の2国間貿易では、輸出者から輸入者へ、船積書類、インボイス、パッキングリストなどの書類一式を送ります。
しかし、3国間貿易では、書類は輸出者から仲介業者へ送付されます。
詳しくは後ほど説明しますが、3国間貿易では、仲介業者は輸入者に対して下記の情報を公開していません。
- 輸出者についての情報
- 輸出者からの請求金額
そのため、仲介業者で差し替えたインボイスとB/Lを、輸入者に送付しているのです。
スイッチインボイスの詳細
発行者名と、インボイス価格が変更されたインボイスのことを、スイッチインボイスと呼びます。
仲介業者は、インボイス価格にマージンを乗せていることを輸入者に知られないために、インボイスの差し替えを行います。
例えば、輸出者から仲介業者へのインボイス価格が500ドルだったとしたら、700ドルに金額を変更したインボイスを輸入者に対して発行するのです。
スイッチB/Lとは?
スイッチB/Lとは、輸出地で発行されたB/Lに記載されているShipper名と、Consignee名を変更したB/Lのことです。
輸出者についての情報を輸入者から隠すためには、仲介業者はフォワーダーに依頼をしてB/Lの差し替えを行う必要があります。これは、B/LのShipper名が輸出者になっているためです。
先ほどの例えをもとに、どのようにB/Lが変更されるかを解説します。
- 輸出者 :マレーシア
- 仲介業者:日本
- 輸入者 :オーストラリア
最初に輸出地で発行されるB/Lでは、Shipperはマレーシアの会社で、Consigneeは日本の仲介業者になっています。
これを、日本のフォワーダーで、Shipperを日本の仲介業者、Consigneeをオーストラリアの輸入者へ変更するのです。
なお、積み地がマレーシア、揚げ地がオーストラリアであることは変わりません。
また、オリジナルB/Lが発行されている場合は、輸出者は原紙を仲介業者へ送付する必要があります。
3国間貿易を、移動距離の短い国同士で行う場合は、迅速に書類を手配することが大切です。書類よりも早く船が輸入地に到着してしまう、などということがないようにしましょう。
3国間貿易のメリットとデメリット
3国間貿易の、輸出者と輸入者にとってのメリットとデメリットについて解説します。
輸出者・輸入者にとってのメリット
3国間貿易では、輸出者と、輸入者双方と取引実績のある会社が仲介業者になっています。
「何か問題があれば仲介業者が責任を持って対応してくれる」という安心感が、輸出者と輸入者双方にあることが、3国間貿易の大きなメリットです。
輸出者と輸入者それぞれに、どのようなメリットがあるかを見ていきましょう。
輸出者にとってのメリット
仲介業者は輸出者と、輸入者双方との取引実績があるため、信用面と代金回収面のリスクを軽減させることができます。
輸出者にとっては、自分たちで輸入者を見つけて、売買契約を締結し、信用面と代金回収面のリスクをなくしていくための、時間とコストを減らせることがメリットです。
輸入者にとってのメリット
輸入者にとっては、新規の取引先と支払い金額や条件を直接交渉するよりは、仲介業者に取りまとめてもらう方が有利に商談を進めることができます。
信頼できる仲介業者を通して取引を行うことで、製品を受け取れない、または、不良品をつかまされるリスクを回避できることもメリットの一つです。
また、第三国を経由することでの時間的・経済的な輸送コストや、関税・消費税の発生を回避することもできます。
3国間貿易のデメリット
3国間貿易を行うためには、「情報のリスク管理をしなければならない」というデメリットがあります。
輸入者に仕入れ価格と、仕入先を知られてしまうリスクがある
仲介業者はマージンを乗せていることを、輸入者に隠す必要があります。
仲介業者で差し替える前のインボイス価格を輸入者に知られてしまうと、マージンをいくら乗せているかが判明してしまうため、輸入者からの不信を招くことになるでしょう。
「これなら直接取引した方が良い」と輸入者に思わせないためにも、情報のリスク管理を徹底することが必要です。
原産地証明書に輸出者名が記載されている
EPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)による輸入時の関税減免を受けたい場合は、輸出国で発行した特定原産地証明書が必要になります。
特定原産地証明書とは、輸入される製品が、EPA、または、FTAを結んでいる国で製造・加工されたものであることを示す書類です。
特定原産地証明書を輸入通関時に提出することで、一般税率よりも低い特恵関税(減税・無税)を適用してもらえます。
EPA、または、FTAが締結されている国同士間での輸出入であれば、たとえ仲介業者が入っていたとしても、輸入された製品に対して特恵関税を適用させることは可能です。
しかし、原産地証明書には輸出元の情報が記載されているため、輸入者に輸出者の情報が知られる原因となってしまいます。
取引契約を結ぶ前に、特定原産地証明書が必要になるかを確認しておきましょう。
まとめ
3国間貿易は、2国間貿易に比べると書類とお金の流れが若干複雑で、情報リスクの管理を徹底する必要はありますが、輸出者・仲介業者・輸入者にとってメリットのある貿易形態です。
また、FTAやEPAの利用や、税率が低い国を第3国にすることで有利に貿易取引を進めることも可能です。
3国間貿易は、有効な貿易取引形態の1つとして活用できるものです。
この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら!