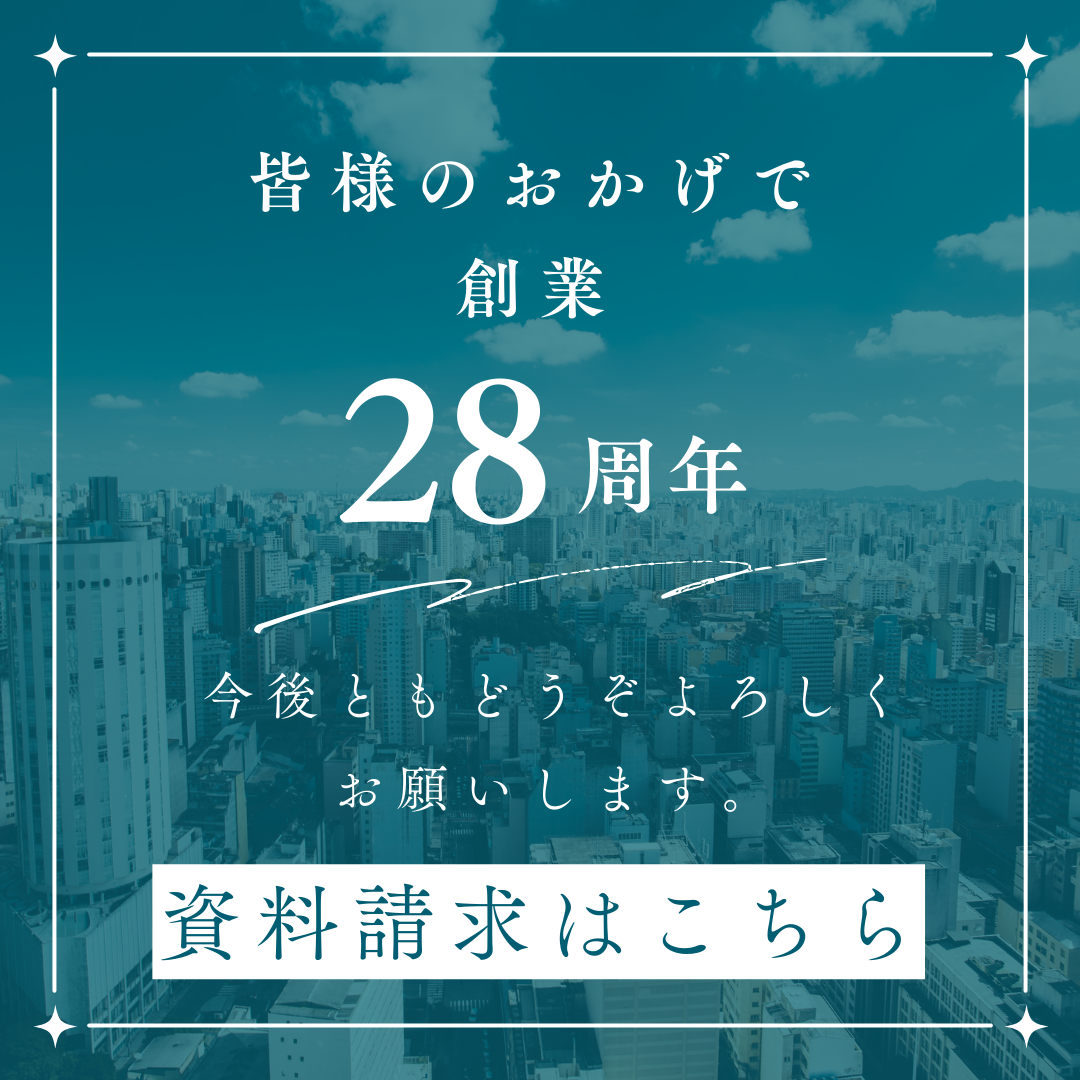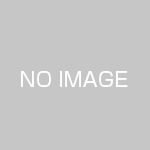国際輸送を検討する際、多くの企業が直面するのが「チャーター便にするべきか、それとも混載便にするべきか」という選択。
どちらを選択するかでコストや納期、荷物の内容に大きな影響を与えるため、適切な選択が求められます。
本記事では、チャーター便と混載便の基本的な仕組みから、それぞれのメリット・デメリット、そしてケース別の使い分け方までをわかりやすく解説します。
目次
チャーター便とは?
チャーター便は一般的には「貸切便」とも呼ばれ、大きな貨物、緊急性や機密性、または特殊な輸送条件が求められるケースで選ばれることが多いです。
まずは、チャーター便の仕組みと活用されるシーンについて見ていきましょう。
チャーター便の基本的な仕組み
チャーター便とは、トラックなどを丸ごと1つで借り切って貨物を輸送する手法で、同一の便に他社の貨物が混載されることはなく、完全なプライベート輸送となります。
「専用車両」として輸送体制が組まれ、発着スケジュールやルートの柔軟な設定が可能になります。
たとえば、製造業のA社が海外の展示会に出展するため、大型機器や展示パネルなどを納期厳守で送りたいとします。
このようなケースでは、通常の混載便では間に合わないリスクがあるため、チャーター便が選ばれることが一般的です。
したがって、チャーター便は、「時間」「空間」「安全性」のいずれにおいても独自のメリットを提供する輸送手段と言えるでしょう。
チャーター便が選ばれる主なシーン
チャーター便が選ばれる場面には、いくつかの代表的な特徴があり、以下のような状況でチャーター便の導入が強く検討されます。
・貨物サイズがいびつなとき
混載便では組み込みにくいものや重量が大きものは、断られるケースが多いです。
・緊急輸送が必要なとき
医療機器や部品など、日時が遅れると損失が大きくなる場合。
・特殊サイズや重量物の輸送
他社と共同での輸送が難しい大型設備などを運ぶ際。
・危険物の輸送
混載が制限される化学薬品やバッテリーなど。
混載便とは?
一方の混載便は、複数の荷主がひとつのトラックを共同で利用するスタイルの国際輸送です。
コスト面でのメリットが大きく、特に小ロット輸送を行う企業にとって、効率的な輸送手段として広く活用されています。
ここでは、混載便の仕組みと、どのようなケースで利用されるのかを見ていきましょう。
混載便の基本的な仕組み
トラックによる混載便は、「LTL(Less Than Truck Load)=トラック積載量未満」の貨物を対象とした輸送方式で、複数の荷主が同じトラックの荷台スペースをシェアする仕組みです。
1社単独ではトラック1台分を埋められない場合でも、他社の貨物と一緒に積載されることで、効率的かつ低コストな輸送が実現します。
混載便の一般的な流れとしては、まず各荷主の貨物が集荷拠点または中継センターに持ち込まれます。
そこで貨物は積載順や配達先に応じて仕分けされ、同じ方向・地域への荷物と組み合わされて1台のトラックに積まれます。
その後、複数の配送先を巡回する「ルート配送」形式で、順次貨物が降ろされていきます。
混載便方式では、1社あたりの輸送コストを大幅に削減できるのが大きなメリットであり、
出荷頻度が高くても、1回あたりの荷量が少ない企業にとっては、コストと利便性のバランスが取れた輸送手段です。
ただし、複数の荷主の貨物をまとめる関係上、積み替えや仕分けの回数が増え、到着までのリードタイムは長くなりがちです。
また、他社貨物との接触リスクも考慮が必要なため、輸送品質を求める製品やデリケートな商材には注意が必要です。
混載便が適しているケース
混載便は、以下のような場面で特に効果を発揮します。
・輸送量が少ないとき
1回の出荷量がパレット数枚以下や、ダンボール数個程度といった小口貨物を定期的に送る企業には、混載便が最適です。
自社専用のトラックを手配するよりもはるかに安価で済み、配送コストの無駄がありません。
・コストを重視したいとき
チャーター便に比べて費用が大幅に抑えられるため、予算が限られている場合やコスト最適化を目指す企業にとって有利です。
. スポット出荷や試験出荷の段階
商品発売前のテスト出荷や初回の少量出荷などでは、混載便を使って利用し様子を見ながら輸送計画を立てるのが有効です。
チャーター便のメリット・デメリット
チャーター便は、スピードや柔軟性を最大限に発揮できる輸送手段として、高い信頼性を誇る一方で、コストや運用面での課題も存在します。
ここでは、チャーター便の主なメリットとデメリットについて詳しく解説します。
チャーター便のメリット
チャーター便の最大の利点は自由度と独占性の高さにあり、主に以下のようなメリットが得られる点が大きな特徴です。
- 納期の自由度が高い
チャーター便は到着日時を柔軟に設定できるため、特定の納期に合わせて輸送スケジュールを調整できます。
展示会やキャンペーン時の製品搬入など、「この日までに確実に届けたい」というニーズに強く応えます。 - 輸送リスクが低減される
貨物が他社と混載されないため、破損や紛失、誤配送などのリスクが極めて低くなります。
また、貨物の積み替えや中継も少ないため、荷崩れの心配も最小限に抑えられます。 - 特殊な貨物にも対応可能
大型機械、精密機器、危険物など、通常の混載便では対応が難しい貨物にも柔軟に対応できます。
温度管理が必要な冷凍品や医薬品、大型重量物の航空輸送など、特別仕様が求められる輸送において特に適しています。
チャーター便のデメリット
魅力的なチャーター便にも、いくつかのデメリットが存在し、導入を検討するうえでは以下の点に注意が必要です。
- コストが高い
最大のデメリットは費用面です。
一台、または一便を丸ごと専用で使用するため、貨物量が少ない場合には割高になってしまいます。
輸送効率よりもスピードや安全性を重視する場合に適していますが、コスト管理が厳しい企業には負担になることもあるでしょう。 - 輸送機材の手配に時間がかかる場合もある
人気のある時期(繁忙期)や緊急性が高い場合、チャーター便の手配が困難になるケースもあります。 - キャンセル時のリスクが高い
チャーター便は一度手配すると、キャンセル時に1台分のキャンセル料が発生する可能性があるため、急な予定変更やキャンセルリスクがある場合は慎重な判断が必要です。
このように、チャーター便は「価格に見合う価値があるかどうか」が判断の分かれ目となります。
緊急性・特殊性がある輸送であればあるほど、チャーター便のメリットが際立ちます。反対に、それらの条件が不要な場合は過剰なコストを支払うことになりかねません。
混載便のメリット・デメリット
混載便は、多くの荷主にとって「費用を抑えた国際輸送手段」として定番となっています。
しかし、その分だけ制約やリスクもあるため、メリットとデメリットの両面を理解しておくことが重要です。
混載便のメリット
混載便の最大の魅力は、コストパフォーマンスの高さにあります。
小口貨物を扱う企業にとって、最も導入しやすい選択肢のひとつと言えるでしょう。
- 輸送コストが抑えられる
トラックを複数社で共有するため、輸送費が分割され、1社あたりの負担が少なくなります。
フルチャーターに比べて数分の一、あるいはそれ以下のコストで済むこともあり、特に出荷量が安定しないスタートアップや中小企業には大きな利点です。 - 小口貨物に対応可能
1個口・数個口といった少量の出荷にも柔軟に対応してくれるため、頻繁な少量出荷にも適しており、倉庫に余剰在庫を持たない企業にとって非常に有効な輸送手段で
混載便のデメリット
一方で、混載便には制約も存在し、特に時間や管理面での柔軟性に欠ける点は大きな注意点です。
- 納期が固定されやすい
定期便のスケジュールに合わせて出荷するため、チャーター便のような柔軟な時間指定は難しい場合があります。 - 他社貨物との混載によるリスク
他社の荷物と同じ空間で運ばれるため、万が一の破損や液漏れ、臭気などの影響を受ける可能性があります。
また、通関の際に一部の貨物に問題があると、全体の輸送が遅延するケースもあります。 - 仕分け・積み替えの回数が多い
混載便は複数の荷主の貨物をまとめて積み下ろしするため、途中で何度か仕分けや積み替えが行われる際に、破損や紛失のリスクが増加する可能性があります。 - 管理しづらい貨物には不向き
温度管理が必要な商品、厳格な品質基準が求められる精密機器などは混載便では対応が難しいことがあり、こうした貨物は個別対応できるチャーター便のほうが適しているでしょう。
チャーター便と混載便、選び方のポイント
チャーター便と混載便は、それぞれに異なる特性を持つ輸送手段であるため、自社の物流ニーズや貨物の特性に応じて、適切な輸送方法を選ぶことが重要です。
ここでは、選択の際に押さえておきたい判断基準と、代表的な使い分け事例をご紹介します。
判断基準
まず、どちらの便が適しているかを見極めるために、以下の4つの観点から検討しましょう。
- 貨物の量・サイズ・重量
貨物が大量、もしくは大型で他社と混載できない場合はチャーター便が適しています。
一方で、少量であれば混載便の方が効率的です。 - 納期の厳しさ
「いつまでに届けなければならない」という明確な期限がある場合、スケジュールを自由に設定できるチャーター便が有利です。
一方、ある程度の猶予があるなら混載便でも問題ありません。 - 予算・コスト感
輸送コストが大きなウエイトを占める場合は、混載便の方が断然有利です。
チャーター便を選ぶ際は、必要な品質やスピードへの対価として、費用対効果のバランスを見て判断することが求められます。 - 貨物の性質(機密性・脆弱性など)
精密機器や試作品など、他社との混載によるリスクを避けたい場合は、専用の輸送空間を確保できるチャーター便が適しています。
それら以外の一般的な製品であれば、混載便でも十分なケースが多いでしょう。
ケース別の使い分け例
判断を明確にするために、実際に想定されるシーン別に、チャーター便と混載便のどちらが適しているかを見ていきましょう。
ケース1:展示会出展のための緊急輸送
展示会での出展に必要な製品や機材を「○月○日までに確実に届けたい」という場合、時間の自由度が高く、遅延リスクの少ないチャーター便が最適です。
ケース2:定期的な少量出荷
毎週一定量の製品を海外取引先へ送るようなケースでは、混載便がコストパフォーマンスの面で優れています。
定期便として運用できるため、計画的な物流にも対応可能です。
ケース3:スタートアップによる小ロット海外販売
立ち上げ間もない企業が海外向けに少量ずつ製品を出荷する場合、混載便の低コスト輸送は非常に費用対効果が高いです。
初期投資を抑えられるため、販路を広げる戦略に適しています。
ケース4:危険物や特殊貨物の取り扱い
危険物、あるいは温度管理が必要な特殊な貨物は混載が制限されることがあるため、専用輸送ができるチャーター便が安心です。
このように、輸送手段の選択は「どちらが優れているか」ではなく、「どちらが自社の状況に合っているか」を見極めることが重要です。
最適な選択ができれば、コスト削減・納期遵守・品質確保のいずれにも良い効果をもたらすでしょう。
まとめ
貨物輸送における「チャーター便」と「混載便」は、それぞれ明確な特徴と役割を持つ輸送手段です。
チャーター便は、スピードと安全性、柔軟性を重視する輸送に最適であり、混載便はコストパフォーマンスを追求する輸送に強みを発揮します。
どちらを選ぶべきかは、貨物の量や性質、納期、コスト、リスク管理の必要性など、輸送の条件や目的によって大きく異なります。
そのため、「とにかく安く」や「とにかく早く」といった単一の基準ではなく、総合的な観点で考える必要があります。
貴社にとって最適な輸送方法を選び、より効率的で確実なビジネスを実現していくために、ぜひ本記事の内容を参考にしていただければ幸いです。