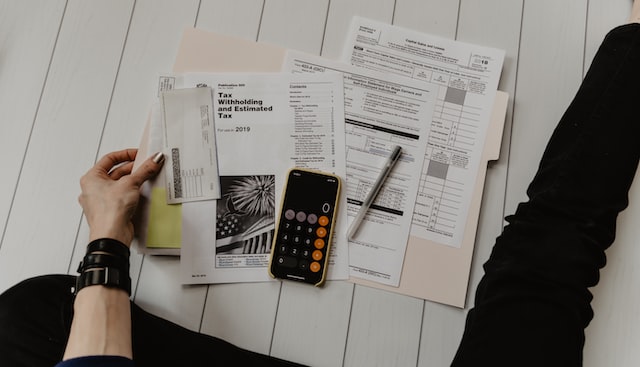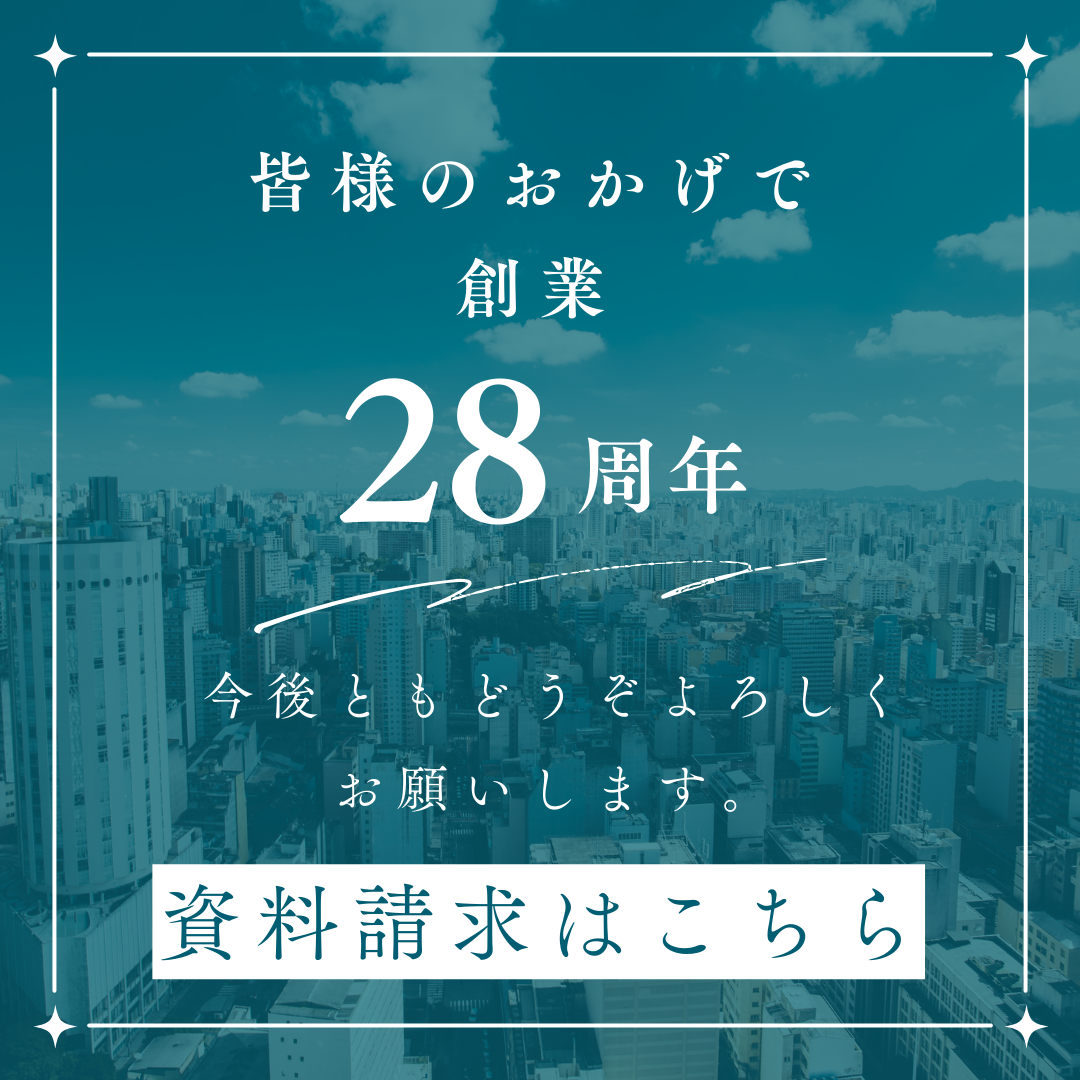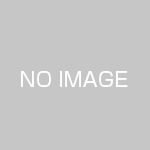物流業務ご担当の皆様、従価税と従量税という言葉をご存知でしょうか?
これらは輸入関税を計算する際に出てくる言葉です。倉庫会社や輸送会社といった通関業者に輸入申告の代行を依頼していると、基本的には業者が関税計算もまとめて対応してくれますので、ご存知ない方も多いかもしれません。
今回は、関税制度の基本である輸入関税の計算方法についてご紹介します。
目次
関税とは?基礎から解説
今日の日本における関税とは、輸入品に課される税のことで、外国から到着した貨物を日本に引き取る際に課されます。
・納税義務者
関税の納税義務者は、貨物を輸入する者と規定されています。
輸入者はその通関業務を通関業者に委託することができますが、以下の点に注意が必要です。
- 関税の計算精度
通関業者が計算を行う場合でも、輸入者として関税額の正確性を確認する必要がある。
間違った申告をしてしまうと、追徴課税やペナルティの対象となる可能性がある。 - EPA利用時の納税者の責務
経済連携協定(EPA)を活用する場合、輸入者は関税の免除や軽減を受けるために必要な原産地証明書・原産品申告書を税関に提出する。
例えば、日本とベトナムのEPAでは、一定条件を満たした繊維製品の輸入において関税がゼロになる場合がある。
EPAを利用するためには、証明書の内容を正確に確認し、提出期限を守ることが求められる。
・実行関税率表
具体的に、輸入品目ごとにどのように関税率が設定されているのかは、実行関税率表によって確認する事ができます。
この表は税関のホームページに掲載されています。
年に数回改正されていますので、都度確認が必要です(2022年は計5回)。
輸入者は以下の手順を踏むことで、適切な税率を確認できます。
- 税番(統計品目番号)の特定
実行関税率表に記載された税番を用いて、輸入品が該当する関税率を調べます。 - 税率の確認
税率には基本税率とEPA税率が含まれます。
EPA税率を利用する場合、必要な手続きを事前に行うことで大幅なコスト削減が可能です。
例えば、2022年のあるEPAでは、農産物の関税が通常の30%から10%に軽減されるケースがありました。
輸入者は、こうした情報を常に把握し、関税の適切な申告とコスト管理を行うことが重要です。
出典:税関ホームページ 実行関税率表
関税の計算方法|従価税・従量税・混合税の違い
関税額を計算する際、輸入貨物の価格または数量がその計算の基礎となります(課税標準)。
輸入貨物の価格を基準に関税を課すものを「従価税」、数量を基準に関税を課すものを「従量税」と言います。
関税率と同様、課税標準についても輸入品目ごとに設定されており、実行関税率表で確認できます。
・従価税
従価税は、輸入貨物の価格に基づいて計算されます。
実行関税率表では、「〜%」という形で表記されています。
例:衣類の輸入
衣類を1,000,000円分輸入した場合、関税率が10%であれば以下の計算になります:
1,000,000円 × 10% = 100,000円
ポイント:EPAを活用した軽減例
たとえば、日EU EPAに基づき、特定の繊維製品の関税率が通常10%から5%に軽減されるケースがあります。
同じ1,000,000円分の輸入でも関税額は:
1,000,000円 × 5% = 50,000円 と大幅に削減されます。
・従量税
従量税は、輸入貨物の個数、容積、重量など数量を基準に課されます。
肉、魚、酒類など、品目ごとに異なる基準が設定されています。
実行関税率表では、「〜円/L」や「〜円/kg」という形で表記されています。
従価税に比べて課税標準が明確なので、関税額の算出が容易です。
例:コーヒー豆の輸入
焙煎されていないコーヒー豆を10kg輸入し、1kgあたり関税が300円の場合:
10kg × 300円 = 3,000円
・混合税
混合税は、従価税と従量税を組み合わせて算出する方式です。
この方式は少ないですが、主に特定品目に適用されます。
- いずれか高い方(または低い方)を適用
例:課税価格の10%または1kgあたり300円のうち、高い方を採用。- 課税価格が10,000円で重量が30kgの場合:
- 従価税:10,000円 × 10% = 1,000円
- 従量税:30kg × 300円 = 9,000円
→ 従量税が適用
- 課税価格が10,000円で重量が30kgの場合:
- 両方を足し合わせる方式
例:課税価格の5% + 1kgあたり200円- 課税価格が10,000円で重量が20kgの場合:
- 従価税:10,000円 × 5% = 500円
- 従量税:20kg × 200円 = 4,000円
→ 合計 4,500円
- 課税価格が10,000円で重量が20kgの場合:
適用例:綿織物
混合税は毛織物、卵黄、魚油、鉛合金の塊など、一部の工業製品に適用されることがあります。
実行関税率表で詳細を確認しましょう。
実行関税率表で確認してみよう
関税率は貨物の種類によって非常に細かく設定されています。
実行関税率表を正しく読み解くことが、輸入におけるコスト管理の鍵となります。
ここでは、焙煎されたコーヒー豆(カフェインを除いていない)を例に、関税率の確認方法を解説します。
分類を調べよう
実行関税率表は、貨物を第1類から第97類までの分類に分けています。
商品がどの類に該当するかを最初に特定します。
例:焙煎されたコーヒー豆(カフェインを除いていない)
該当する類: 第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)
こうして、輸入品の大まかな分類を確認します。
統計品目番号を調べよう
次に、類の中でさらに細分化された「項」と「号」を確認します。
最終的に9桁の「統計品目番号」が決定されます。
例:焙煎されたコーヒー豆(カフェインを除いていない)
統計品目番号: 0901.21-000
この番号は、輸入申告時に必ず使用するため、正確に確認しましょう。
間違えると適用される税率が変わるため、注意が必要です。
焙煎されたコーヒー豆の関税率
統計品目番号が決定したら、実行関税率表を見て適用される税率を確認します。
焙煎されたコーヒー豆(カフェインを除いていない)の基本税率: 20%(従価税)
計算例
課税標準価格が1,000,000円の場合:
1,000,000円 × 20% = 200,000円
焙煎されていないコーヒー豆の関税率
焙煎されていないコーヒー豆(生豆、カフェインを除いていない)の場合、統計品目番号は0901.11-000です。
驚くべきことに、この品目の基本税率は無税です。
比較例
課税標準価格が1,000,000円の場合、焙煎されたコーヒー豆と焙煎されていないコーヒー豆の関税額は以下の通りです:
焙煎されたコーヒー豆: 200,000円
焙煎されていないコーヒー豆: 0円
焙煎の有無で関税額に20万円もの差が生じることになります。
EPA税率を活用する場合
例えば、EPA協定税率を適用することで、焙煎されたコーヒー豆も無税で輸入することが可能です。
ただし、原産地証明書などの書類提出が必須となります。
・修正申告と更生申告
統計品目番号の決定は非常に重要であり、誤ると納める関税額が過不足になります。
不足の場合: 修正申告を行い、不足分に加えて過少申告加算税を納付します。
過剰の場合: 更生申告を行い、過剰分の返還を受けます。
このようなトラブルを避けるためには、統計品目番号を慎重に決定することが重要です。
・事前教示制度
統計品目番号の決定に悩んだ場合は、「事前教示制度」の利用を検討しましょう。
これは輸入前に税関に問い合わせることで、統計品目番号や適用税率についての回答を受けられる制度です。
利用方法
文書、メール、口頭での問い合わせが可能です。
事前に照会することで、適切な申告が可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
実行関税率表を正しく利用することで、輸入品目に適した税率を確認でき、適切な関税額を計算できます。
焙煎の有無やEPAの利用による関税額の差を把握することで、輸入コストを大幅に削減することも可能です。
輸入業務をスムーズに進めるために、統計品目番号の確認や事前教示制度の活用を徹底しましょう。